
最愛の亡き妻がいる魔王(あなた)には、好きって言われたくありません!
- 発売日2023.07.14
- 価格¥858(税込)
※価格や発売日はストアによって異なります。
早く俺を好きになれ。
私は書記官見習いのカレン。最近とんでもないことが起こりました。空から魔王が降ってきて、私の家に居候するって言うんです……。人間なんて小指の一振りで殺せちゃう最強生物の「お願い」を断れるはずがありません。泣く泣く同居を始めましたが、この魔王、魔王のくせに料理も他の家事も完璧。しかも危ないときは助けてくれて、スパダリ感が半端ないです。その上、なんだか私のこと……口説いてません……? 過去に最愛の奥さんを亡くしてるくせに。そんな立場で迫ってこないでください! 私は本気にしませんから、絶対本気にしませんからね!
電子書籍購入サイト
人物紹介
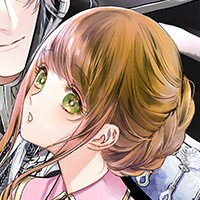
-
カレン
書記官だった亡き父を目指し、書記官見習いとして日々仕事に励んでいる。なぜか魔王に居候をされる羽目になるが、魔王のつくる料理がおいしいのでほだされかけている。

-
魔王
ある日突然、空から降ってきた超絶美形の最強魔王。大変なスパダリ属性で、なぜか甲斐甲斐しくカレンの世話を焼く。カレンに付きまとうのには、ある理由があり……。
試し読み
――うちの前に立ってるの誰? 見覚えがある……あの銀の髪に紅の目……。
私はしばし呆然とした。
いや、嘘でしょ、なんで魔王が私の部屋の前にいるの!
歯の根が合わないほどガタガタ震えながら、私は思った。
――なんでここにいるの!
絶世の美貌に笑み一つ浮かべず、魔王は淡々とした口調で私に言った。
「今日からここに居候したい」
「……?」
それはどういうことですかね。まったく理解できないんですが。
そう思ったけど、ブルブル震えるだけでなんにも聞けなかった。
仕方ない。だって私、ただの書記官見習いだし、魔法なんて使えないもの。魔王に対抗する術なんてなにも持ってない。
――どうしよう、どうしよう、どうしよう……。
だが私には頼れる両親もなく、逃げる場所もない。私にあるのは寮のこの部屋と、父さんが残してくれたペンだけだ。
どうにもならない。そう腹を決めた私は素直に扉を開け、魔王を招き入れた。
「どうぞおあがりください」
それ以外にどうすればよかったのだろう。怖すぎて、私にはこれ以外の対応を思いつかなかったのだ。
「お招きありがとう。居間はどこにあるのだ?」
「あ、あの、ここ、独身寮なので……見えてる範囲がすべてで、お手洗いとお風呂は共同です」
部屋の説明をする私に、魔王はにっこり笑った。
「なるほど。慎ましくてよい部屋だ。では今日からお世話になる」
――え、えええええっ、どうしよう……! どうしよう!
だめだ。
無難にお帰りいただく方法を考えようとしたが、脚が震えるだけで頭がまったく働かない。
「カレン」
教えてないのに、魔王は私の名前を知っているようだ。
どういうことなんだろう。これもなにかの魔法だろうか?
半泣きの私に、魔王が自己紹介を始める。
「名乗りたいのだが、我には人間に呼ばせる名前がない。―――という名なのだが、そなたに聞き取れるか?」
「よ、よくわかりません。聞き取れませんでしたので、魔王様と呼ばせていただきます!」
魔王が頷いた。
それでいいらしい。
「あの、ところで、うちはこのように粗末で狭いので、別の家のほうが……」
「いや、ここがいい」
――そうか、ここがいいのか。えー。どうしよう……どうして……?
知恵を絞ろうとしたがなにも案が出てこないな。
魔王は強すぎるから追い出す方法なんてない。助けを呼んでも、誰も魔王に勝てない。
ものすごい諦めが心の底からこみ上げてくる。
とりあえず、魔王の好きにさせよう。私は持ち帰りの仕事をしよう。
「あの……じゃあごゆっくり。私は持ち帰りの仕事をしていますね」
魔王が頷く。
――一回現実を忘れよう……! このどうにもならない現実を……!
そう思いながら私は必死にペンを握った。
震えて、うまく持てない。怖いよ。怖い。魔王になにされるのかな。いきなり『暇つぶしだ』とか言って殺されちゃったりしないかな?
悪い想像ばかりが頭をめぐる。
だが私は、なんとか自分に言い聞かせた。
――仕事を……仕事をするの。今日は歴史に残る大事件が起きた日なんだから、私の手でその記録を書き残さなくっちゃ。
私は魔王を視界から排除して、大きく息を吸った。
――まずは気持ちを切り替え、魔王が家に居候すると言いだしたことは措いといて、と。
馴染んだペンの感触が、私の心を少し穏やかにしてくれる。私はペンにインクをつけ、まだ震えの治まらない手で文字を綴り始めた。
魔王城が上空に現れてから今に至るまでの記録を、記憶が鮮やかなうちに残さなきゃ。
もちろん今日の記録資料は、見習いじゃないベテランの書記官たちが作っている。彼らの作った資料が『公式記録』として王宮に保管されるに決まっている。
だけど、私も書くのだ。
いつか『公式記録』に選ばれるような、きちんとした資料を書けるようになるために。
私は、書記官という仕事に強い愛着を持っている。
なぜなら、私の亡き父も王宮仕えの書記官だったからだ。
大好きだった優しい父。
父はもういないけれど、父が書いた資料たちは『公式記録』として王宮に保管されている。
見習いの仕事でとある資料を探していたとき、私はたまたま、父が残した『公式記録』を見つけたのだ。
綺麗な字に丁寧な文章。
本当に父らしい、きちんとした資料だった。
見つけたときの気持ちが、ぶわっと蘇ってくる。私が知らないことを、もうこの世にいない父が側に立って教えてくれているかのようだった。
――すごく嬉しかった。お父さんの資料に『会えた』こと。書いた人はいなくなっても、誰かの役に立つ資料は残る。私もあんな仕事がしたい。
書記官の仕事は『後世に残る』のだ。
私はそのことに、深い意義を覚えている。
亡き父に憧れて目指した仕事だけれど、父が残した記録を見て、私も書記官になりたいと改めて強く思ったのだ。
その気持ちは、魔王に居候されそうな今も変わらない。
頑張ろう、頑張る。いい記録を残して、絶対に見習いから昇格するんだ!
いつしか私は時を忘れ、今日の一連の事件をびっしりと紙に書き記していた。
必死にペンを走らせていると、目の前に皿が置かれる。
なに……この皿……?
食べ物のいい匂いで、私はハッと我に返った。
「ま……っ、魔王様が食事のご用意をしてくださったのですか……っ……?」
「そうだ」
見れば、お皿にシチューが盛られていた。
二人分。スプーンも添えてある。
まさか魔王がいきなり食事を用意してくれるとは思わなかった。
人間が食べても死なないものだろうか?
まず心配になったのはそのことだ。
でもシチューからは、そこはかとない魔王の好意を感じた。
だってわざわざ用意してくれたんだろうし。熱々そうだし。
もしかしてこれは私に迷惑を掛けたお詫びなのだろうか……。
そう思ったら胃がギュッと痛くなった。家に魔王がいるのは現実で、居座る気満々なのだとはっきり認識できたからだ。
「もうしわけありません、仕事に熱中してしまっていて。こ、これ、どこでご用意なさったんですか?」
独身寮には厨房がない。食堂で食べるか惣菜を買って持ち帰るしかないのだ。でもこの辺にシチューを売っているお店なんてないし、いったいどこで手に入れたのだろう。
「空に我の城があろう? そこの厨房で我自身が作った」
天井を指さしながら魔王が言う。私はつられて汚れた天井を仰ぎ見た。
――気軽に空飛ぶんだな、この魔王……。
魔王は、空に浮いている魔族の城に一時的に戻っていたらしい。
記録作成に集中していたから、魔王がいないことに全然気づかなかった。
「あ、あの、恐れ入ります、お食事のご用意をしてくださるとは思わず……」
頭が真っ白になってしまう。突然押しかけてきたと思ったら、次はご飯をごちそうしてくれるなんて。魔王は本気で人間界を満喫するつもりなのだろうか。
「いい。いつも我が食事の支度をしていたから慣れているのだ」
淡々と魔王が言う。
「普段から、お食事の支度をなさっているのですか?」
「ああ」
この時点で聞きたいことが百個くらい湧いてきたんだけど、もちろん私に聞く勇気はなかった。












