
愛する人は他にいると言った夫が、私を離してくれません (上)
- 発売日2023.07.14
- 価格¥814(税込)
※価格や発売日はストアによって異なります。
なぜ僕は契約結婚を持ちかけてしまったのか……。
十五歳で両親を亡くして以来、幼かった弟の代わりに領主の役目をこなしてきたセラフィーナ。狡猾な大人と渡り合ってきた結果、いつしか彼女は『鉄の伯爵令嬢』と敬遠されるようになっていた。だがある日の夜会で、美貌の公爵メイナードの窮地を救ったことがきっかけで、彼と契約結婚することに。「僕には愛する人がいる」と言い、離婚まで『白い結婚』を貫くことを約束するメイナード。しかし、ともに過ごすうちに、セラフィーナを見つめる彼のまなざしはどこか熱っぽくなってゆき……?
電子書籍購入サイト
人物紹介
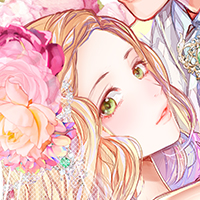
-
セラフィーナ
幼い弟の代わりに領主の役目をこなし、腹黒い大人と渡り合ってきたしっかり者。『鉄の伯爵令嬢』という異名をつけられ、遠巻きにされている。メイナードは少女時代の淡い初恋の相手。

-
メイナード
王の血を引きながらも愛人の子であるため『婚外子公爵』と忌避されている。やや尊大な言動があるものの、公明正大で気持ちの良い性格。幼い頃に会った「レースの天使」が忘れられないでいる。
試し読み
(うむ。こちらの枝をもう少し切っておいたほうがいいな)
結婚式のためとはいえ、枝を切るのだから少しでも形が良いほうがいいだろう。銀梅花の全体的な形を確認しながら顎に手を当てて考えていると、「きゃあ!」と可愛らしい声が聞こえた。
「――ん?」
執事の声ではないな、と振り返ったメイナードは、執事の後ろにいる小柄な女性の姿に目を見張る。
「――セラフィーナ!」
久しぶりに見るセラフィーナは、春らしい淡いベージュとサーモンピンクのデイドレスを着て、顔を背けるようにして立っていた。
「……ごきげんよう、公爵様」
そう挨拶する間も、顔を背けたままだ。
「どうした? 挨拶は顔を見てするものだ」
まるで自分を見るのが嫌だと言われているようで、いささかムッとしつつ訊ねると、セラフィーナが呻くような声を出す。
「……あの、なぜ何も着ていらっしゃらないのです?」
「――ん?」
指摘され、メイナードはようやく自分が上半身裸であることに気づいた。
先ほど銀梅花に追肥を与えようと山ほどの堆肥を運んだ時に、シャツが汗でびっしょりになったので脱いでしまったのだ。
「これは、失礼した。庭仕事をして暑くなってしまって……」
「そ、そうでしたか……」
言い訳をすると、セラフィーナはまだ向こうを向いたままでゴニョゴニョと返す。
本当のことを言えば、メイナードが公爵邸の庭で上半身裸でいることは珍しいことではない。身体を鍛えるために剣術の稽古をしたり、今のように庭仕事をする時に、すぐ上衣を脱いでしまうからだ。
汗をかいた時に、濡れた衣類が肌にくっついている感触が嫌いなのだ。
今もその辺に脱ぎ捨ててあったシャツを拾ったものの、身につける気にはなれず、丸めて執事に手渡した。
「せっかく庭へ出てきてくれたのに悪いが、中へ戻ろう。今は着る物がないんだ」
メイナードが言うと、セラフィーナは一瞬困ったように視線を上げたが、メイナードの裸を目の当たりにすると、またパッと俯いた。
(……これは面白い)
常に冷静沈着で『鉄の伯爵令嬢』と言われている彼女が、自分の裸に狼狽えているらしい。
幼い弟に代わり領主代理をやっていたというから、世慣れた女性だと思っていたのだが、存外初な面もあるようだ。
妙にソワソワとした高揚感が湧いてきて、メイナードは一歩彼女の傍へ近づいた。
するとセラフィーナは、怯えたうさぎが耳を立てる時のように、ピッと背筋を伸ばす。
いつもは青白いその頬が、淡い桃色に染まっていた。
(……はは、なんだ、可愛らしいじゃないか)
自分の結婚相手は、表情に乏しく情緒に欠ける女性だと思っていたが、どうやら少々違うようだ。
メイナードは嬉しくなって、彼女の前に腕を差し出した。
「このような礼を欠く格好で申し訳ないが、邸までエスコートしよう」
「は……あ、あの……」
セラフィーナは差し出された腕とメイナードの顔を交互に見た後、また胸板の辺りに視線を彷徨わせる。
それからもう一度メイナードの顔を見上げ、顔を真っ赤にして諦めたように頷いた。
「……お願いいたしますわ」
この上半身裸の男にエスコートされるというのか、恥ずかしい、どうしよう、でもそれを口にするわけにもいかない――といった心情だろうか。
(可愛いな)
メイナードは頬を緩ませた。
可愛い。実に、可愛らしい。
会ってからまだ数か月しか経っていないし、数えるほどしか会えていないが、セラフィーナがこれほどクルクルと表情を変えるのは珍しい。
(……もしかして、普段の冷静さも本当の姿ではないのでは……?)
メイナードは自分の腕に添えられた小さな手が微かに震えているのに気づいて、ふとそんなことを思った。
全裸だったというならまだしも、男の上半身の裸を見ただけでこの狼狽えようだ。メイナードが今まで見てきた彼女は、上っ面だけだったのかもしれない。
『世慣れた』とメイナードが感じた彼女の印象は、対外的な……いわゆる仮面のようなものなのではないか。
両親が亡くなった時、彼女は十五歳だったという。まだ少女であった頃から大人のふりをしなくてはならなかったのだ。『世慣れた』仮面を被らなければやっていけなかったのだろうことは想像に難くない。
そう考えると、メイナードの胸の中に、彼女に対する憐憫に似た庇護欲が込み上げてきた。
(……この震える手を守ってやりたい、と思うのは、傲慢だろうか)
少なくとも契約結婚を申し出た男が言う台詞ではないな、と自嘲する。
(どの口が言うのだ……)
隣を歩く彼女の小さな頭がずいぶんと下のほうに見える。こうして並ぶと、自分の肩ほどの身長しかない。本当に小柄な女性だ。小柄なだけでなく、全てがか細い。首も腕も折れそうなほど華奢だ。
(……ちゃんと食べているのだろうか……)
そんな余計な心配をしていると、コホンと小さな咳払いが聞こえてきた。
セラフィーナが赤い顔のまま、前を向いて言った。
「今日お伺いしたのは、例の契約についてご相談があったからなのです」
「うん?」
相槌で先を促すと、彼女はチラリと背後についてきている執事を見る。
人払いをしてほしいのだと察し、メイナードは執事に「テラスに茶の準備を」と言いつける。執事は一礼して屋敷へと戻っていった。
執事の黒い後ろ姿が見えなくなるのを確認した後、セラフィーナが小さく息を吐くのを見ながら、メイナードは「それで?」と訊ねる。
「契約結婚の内容に何か不満があったのか?」
あの契約内容は、セラフィーナが損をしないようにと配慮して作ったものだ。だがそれでも至らない部分はあるだろう。
(全ては僕のわがままなのだから、できるだけ彼女の希望を聞いてやりたい)
『レースの天使』が現れるまで、彼女には契約結婚――つまり偽装結婚に付き合ってもらわなくてはならないのだ。
「なんでも言ってくれ。君には負担をかけてしまうのだから、多少の無理をしてでも、希望は叶えるつもりだ」
そう言うと、セラフィーナは黙ったまま視線を上げ、メイナードの顔を見つめてきた。
「……それは本当ですか?」
「ああ、もちろんだ。なんでも言ってくれ!」
胸を張って頷くと、セラフィーナはニコリと微笑んだ。
「では、契約内容の第五条の変更をお願いしたいです」
「第五条……? というと……」
メイナードは頭の中で第五条の内容を探ってみた。だがメイナードが記憶から内容を引きずり出すより先に、セラフィーナがその答えを口にした。













