
公爵は仮初めの妻を逃がさない(下)
- 発売日2024.01.26
- 価格¥792(税込)
※価格や発売日はストアによって異なります。
私は、君が幸せでないと幸せになれない。
オクタヴィアンが爵位を継ぐまでの期限付きの結婚をしたミレーヌ。母親たちの盲目的で奔放な恋愛に、ミレーヌたちだけでなく、多くの者が苦しめられたことを知る彼女は、オクタヴィアンにだけは恋をしてはならないと自戒する。けれど、彼に惹かれる気持ちは日に日に増していくばかり。そんなある日、ミレーヌの献身により、オクタヴィアンが爵位を継ぎ、公爵となることに。オクタヴィアンは、これまで抑えていた気持ちをミレーヌに伝えるが、逆にミレーヌは、オクタヴィアンのもとを離れる決意をして――!?
電子書籍購入サイト
人物紹介
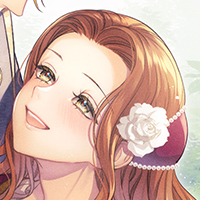
-
ミレーヌ
オクタヴィアンに好意を持ちつつも、自分が側にいると家臣たちと余計な軋轢を生んでしまうため、彼のもとを離れる決意をし……。

-
オクタヴィアン
実母のためにも憎まなくてはならない相手だと分かっていながら、ミレーヌのことを知るにつれ、好ましく思う気持ちを抑えきれなくなってゆき……。
試し読み
「……結婚するつもりがなかったというのは、なぜだ?」
ミレーヌは俯く。
「弟の騎士修行先も見つからなかったのに、それより深い縁を結んでくれる家があろうはずがありません」
ミレーヌはこの公爵領で知らぬ者のいない、悪名高いユージェンヌの娘だ。
「弟が騎士になるのを見届けたら、修道女になってリュネットで司教さまのお手伝いをしようと思っていました」
いつかジャダンドゥールの城を出たら、同じ道を選ぶだろう。
この結婚が無効になれば、宗教上は未婚に戻れるとしても、周囲の目まで何もなかったと見てはくれないだろう。そんな腫れ物のような女と結婚しようという物好きはいないはずだ。
ただひとつ心配なことは、自分のような女といっときでも結婚していたことが、オクタヴィアンの瑕疵にならないかということだった。
「……君の馬を連れて帰ろう」
思いがけない言葉に耳を疑い、ミレーヌは目を瞠る。
「城の厩舎には小さく静かな房もある。馬の世話に慣れた者に手厚く世話させる。君もすぐ会いに行けるようにすればいい」
「でも……」
「慣れた馬は生涯の友だ。とても、また置いていけるようには見えなかった。この裁縫箱もまるごと馬車に載せて行ける。たいしたことじゃない」
ミレーヌはそっと目を伏せた。ミレーヌは遠くないいつかに城を出ることになるというのに、ペルルを連れて行ってもいいのか迷う。
「私は、仮初めであっても、妻になった人にみすみす不自由をさせるほど狭量ではない」
オクタヴィアンは少し早口で強く言った。
そうだ、仮初めの妻なのだ。ほんのいっとき、彼の厚意に甘えても、後には何も残らない。城を出るときは一緒にここに帰ってくればいい。ひとりきりであの城を去るのだと思うと寂しいが、ペルルと一緒に旅立つことができるならどれだけ心強いことか。
「ありがとうございます。……では、連れて行くことにします。明日、乗って行ってもいいでしょうか? 馬車よりは早いと思うのですが」
オクタヴィアンは口の端を緩めて頷いてくれた。
「そうするといい」
そうなれば、支度が必要だ。乗馬服と靴を出してこなければいけない。だが、たくさん話したので、また眠くなってきてしまった。
子どものように目元を擦っていると、ふと、オクタヴィアンが後ろに立っているのに気づく。その手が再び肌に触れ、どきりとする。
「……あの……」
瞬きを繰り返す。
長い指が、ミレーヌの耳の下あたりのピンを抜いていた。
「今にも抜けそうだった。……全部、取っておこうか。寝るのなら、着替えてから寝台に戻ったほうがいい」
小さいあくびを噛み殺したのも、彼に気づかれてしまったらしい。
「はい。……お願いします」
ミレーヌは眠気に抗えず、促されるままに彼に背を向け、少し下を向く。
彼は、うたた寝で乱れたミレーヌの栗色の髪から器用にピンを抜いていった。少しくすぐったいが、とても大切に扱われているような気がして面はゆい。
何だか黙っていられなくなり、口を開いた。
「あの……、わたしは自分の部屋で寝ますね。寝台をお使いください」
「私は長椅子で休むからかまわない。君が部屋を出て行けば、家の者が何事かと心配するだろう」
客室を用意されたのは、家令がオクタヴィアンとミレーヌを夫婦だと信じているからだ。本当は違うのだし、家族同然の館の者たちの手前とても照れくさいのだが、別室に行けばやはり不審に思われるだろう。
ピンを抜き終えた彼が、髪を手櫛で梳き、綺麗にまとめてくれる。その仕草が本当に優しくて、ずっとこんなふうに触れていてもらえたらいいのにと思ってしまう。
かつて彼が髪に挿してくれた、蔓薔薇の白いつぼみ。
あの春のひとときが今もミレーヌにとって美しい記憶であるように、彼と語り合ったこの晩のことも、忘れられない思い出になりそうだった。
ミレーヌはこの人にもう二度と会ってはいけなかったのだろう。
あのときの言葉の意味が、今、本当にやっとわかった。
わかったときには、もう、彼に惹かれる気持ちを止められなくなっていた。












